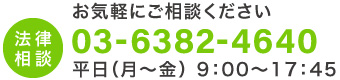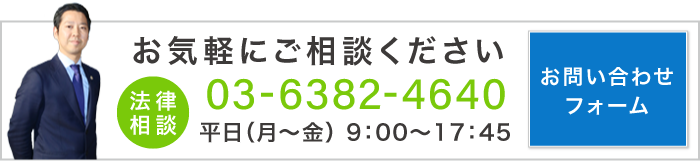目次
相続人に遺留分を「渡したくない」と考えている方へ
遺言書を作成するに当たっては、遺留分(相続人に最低限度保障される割合)に気を付けて作成する必要があります。
遺言書を作成するに当たって遺留分のことを考慮しないと、相続発生後、他の相続人が遺留分侵害額請求を行い、相続紛争が生じてしまう可能性があるからです。
このような遺留分に関する紛争が生じないように、例えば、遺留分相当額の遺産を他の相続人に対して相続させることが考えられます。
もっとも、事情によっては、遺留分すらも渡したくないというご家庭があるのもの事実です。
それでは、法律で遺留分の制度が定められているにもかかわらず、相続人に遺留分を渡さない方法があるのでしょうか。
本ページでは、相続人に遺留分を渡したくない場合において、遺留分を全く渡さない方法と実質的に遺留分を減らす方法等、遺言者が今後とりうる方法について解説を行います。
▼遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法についてはこちらのページをご参照ください。
▼遺言書作成を弁護士に依頼するメリットはこちらのページをご参照ください。
▼遺言者が認知症であった場合における遺言書の作成方法についてはこちらのページをご参照ください。
遺留分とは?請求される金額の計算方法の基礎知識
1. そもそも遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に対し、被相続人の生前の意思に関わらず、法律上最低限保障されている遺産の取得割合のことです。
例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言書を作成しても、他の法定相続人(配偶者や次男など)は、この遺留分に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持っています。これが、遺留分対策が不可欠である最大の理由です。
2. 遺留分権利者となるのは誰か
遺留分を請求する権利を持つ人(遺留分権利者)は、以下のとおり、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
-
配偶者
-
子(子が既に死亡している場合は、孫などの代襲相続人)
-
直系尊属(親や祖父母。ただし、子や代襲相続人がいない場合のみ)
3. 遺留分額の基本的な計算式
遺留分権利者が請求できる具体的な金額(遺留分額)は、以下のシンプルな構造で計算されます。
(※厳密には生前贈与や負債も考慮されますが、ここでは基礎を理解するため単純化しています。)
【計算例】
例えば、遺産総額が1,000万円で、法定相続人が長男と次男の2人のみ(法定相続分はそれぞれ1/2)の場合を考えます。
このとき、長男に対して「全財産(1,000万円)を相続させる」という遺言書を作成した場合、次男が請求できる遺留分額は以下のように計算されます。
次男は長男に対し、250万円の遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分を渡したくない場合、この「遺留分額」をいかにゼロに近づけるか、または減らすかが対策の鍵となります。
相続人に遺留分を渡さない方法
それでは、遺留分を渡さない方法としてはどのようなものがあるでしょうか。
相続人に遺留分を渡さない方法としては、
- 遺留分を全く渡さない方法
- 遺留分を渡さないわけではないが遺留分を減らす方法
があります。
もっとも、次に述べる通り、遺留分を全く渡さない方法は実効性が乏しいので、お時間のない方は、遺留分を減らす方法から順次各自解説を行います。
遺留分の事前放棄により遺留分を行使されなくなる
まず、遺留分を渡さない方法として遺留分の事前放棄を行うという方法があります。
遺留分の事前放棄とは、被相続人の生前において、遺留分請求権者が家庭裁判所に対して遺留分の放棄の許可を求める手続になります。
遺留分権利者である相続人が被相続人の求めに応じて当該申立て手続を行ってくれる場合は、当該手続を利用することにより、遺留分を渡さなくても済むことになります。
もっとも、遺留分権利者が申立てを行う必要があるため、遺留分権利者がこれを拒絶すれば事前放棄はできないことになります。
遺言書における付言事項において遺留分を行使しないよう記載する。
厳密にいえば遺留分を渡さない方法ではないですが、遺言書の付言事項(平たく言えば、遺言書に記載される遺言者からのメッセージです。)に遺留分を行使しないよう要請する方法があげられます。
もっとも、付言事項に遺留分を行使しないよう記載したとしても、法的に遺留分の行使を妨げられるものではありません。
したがって、遺留分請求権者に対する事実上の効果を期待する程度のものになるため、こちらも遺留分を渡したくないというニーズにはマッチしていないと言えます。
廃除や欠格では遺留分を渡さない方法としてあまり意味がない。
なお、遺留分を渡さない方法として、廃除や欠格の制度が紹介されることがあります。
廃除とは、被相続人に対し重大な侮辱等を行った相続人の相続権を失わせる制度になります。
また、欠格とは、欠格事由が存在する場合に法律上当然に相続権を失う制度です。
廃除や欠格の制度によって当該事由の存する相続人は相続権を失い、それにより遺留分の請求もできないことになります。
もっとも、廃除や欠格事由が存し、相続権を失ったとしても、当該相続人に子がいる場合は、代襲相続が発生することになります。
つまり、廃除事由等が存在しても、当該相続人から遺留分の請求を受けないのみであり、その子からの遺留分の請求は受ける可能性があることになります。
したがって、廃除や欠格では遺留分を渡したくないというニーズにはマッチしないことになります。
遺留分を渡さない方法のまとめ
以上のとおり、遺留分額を渡さない方法としては複数考えられますが、実効性は小さいため、次にあげる遺留分額を減らす方法を検討した方が良いと言えます。
相続人の遺留分額を減らす方法
それでは、遺留分額を渡さないために遺留分額を減らすにはどのような方法をとればよいでしょうか。
遺留分額を渡さないために遺留分額を減らすためには、
- 遺産を減らすか
- 法定相続割合を低くする
方法のいずれかをとる必要があります。
これを考える前提として、前述した遺留分権利者が請求できる金額の計算方法を理解する必要があります。
前述の通り、遺産が1000万円、法定相続人が子供2名(法定相続割合各2分の1)の場合において、1名の子供に財産の全てを相続させる旨の遺言が残されたときは、下記の計算式の通り遺留分額は250万円になります。
1000万円(遺産※1)×2分の1(法定相続割合)×2分の1(遺留分割合)=250万円(遺留分額)
※1 厳密にいえば遺産のみではありませんが、ここでは単純化して遺産のみとしています。
したがって、遺留分額を減らすためには、①遺産を減らすか②法定相続割合を小さくする方法を検討することになります。
養子縁組を利用して相続人の遺留分額の支払を減らす
養子縁組を利用すると、養親と養子との間に法律上の親子関係が発生し、遺留分請求権者の法定相続割合が小さくなるため遺留分額を減らすことができます。
例えば、被相続人の法定相続人は長男及び次男であるところ、被相続人が孫(=長男の子)と養子縁組をした場合、長男らの各法定相続割合は2分の1から3分の1に小さくなります。
各法定相続割合が減ると、それによって各相続人の遺留分額も減らすことができます。
このように、養子縁組を行うことによって渡さなければいけない遺留分額を減らすことができますが、デメリットとしては、遺留分対策のために養子縁組を行うことについては心理的抵抗があるということです。
また、養子縁組を行うにあたっては、養子縁組が無効にならないように気を付ける必要があります。
相続目的があるからといって必ずしも養子縁組が無効になるわけではありませんが、縁組の効力が争われないように気を付ける必要があります。
▼ 養子縁組の無効事由や手続きについてはこちらのページを参照ください。
金融資産を生命保険に変更して相続人の遺留分額の支払を減らす
金融資産から生命保険に財産の種類を変更し、それにより遺産額を減らすことによって遺留分額を減らすことができます。
預貯金等の金融資産と異なり、生命保険は保険会社から受取人に対して直接支給されるものであるため、一部を除き遺産ではありません。
したがって、現在存在する金融資産を、例えば一時払いの保険に変えることによって、資産価値を大きく変えずに遺産から外すことができます。
注意点としては、金融資産はご本人が生活するうえでも必要になりますので、全額を保険に変更することはできないという点があげられます。
また、相続人が受け取る保険金額の割合があまりにも大きい場合は、例外的に、特別受益(被相続人からの生前贈与等)として遺産に加えられてしまうという点です。
したがって、この方法を利用する際には、生命保険が特別受益に該当しないか等を判断するために、相続に強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
生前贈与と相続放棄を併用する相続人の遺留分額の支払を減らす
遺留分を渡さないための方法として、最後の方法は、生前贈与と相続放棄を併用するものです。
この方法は、生前贈与を行い遺産額を減らすことによって遺留分対策を行う方法です。
相続法が改正前は、相続人に対する贈与がいつ行われたかにかかわらず、生前贈与額が遺産に加えられました。
しかし、今般の相続法の改正により、相続開始前10年間の贈与のみが遺留分算定の基礎財産に加えられることに変更になりました。
したがって、遺言者・被相続人がある程度お元気なうちから生前贈与を行い、遺産を減らすことによって遺留分額を減らすことが可能になります。
また、仮に相続開始10年以内の贈与であっても、相続放棄を利用する方法もあります。
相続開始から10年遡る贈与は相続人に対する贈与に限られるところ、相続放棄を行った場合は、相続開始時に遡って相続人ではなくなります。
そのため、贈与額が遺産に加えられず遺留分額を減らせる可能性があります。
もっとも、相続人以外に対する贈与であっても、遺留分権利者を害することを知って行われた贈与については遺留分の基礎財産に含まれます。
したがって、この方法を利用するときには、やはり弁護士にご相談された方が良いです。
最後に
以上、相続人に遺留分を渡したくない場合に取りうる方法について解説を行いました。
法律の原則では遺留分を渡さなくてはなりませんが、それでも遺留分を渡したくないご事情のある方がいることを踏まえ、本コラムを作成しました。
本コラムでは相続発生前の遺留分の事前対策の方法について解説を行いましたが、既に相続発生が発生した場合であってもとりうる方法はあります。
遺留分対策のための遺言書作成や遺留分を請求された場合等でお困りの方は、相続問題を重点的に扱う東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。