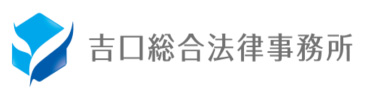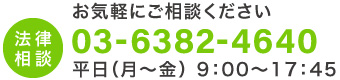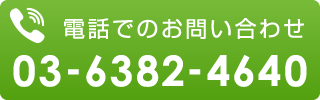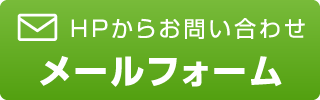Author Archive
障害ある子供に親の死後に財産管理をする方法
障害のある子供の財産管理のために成年後見を利用する方法
成年後見制度のメリット
成年後見制度のデメリット
民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については・・・・
任意後見契約を利用した障害のある子の財産管理を行なう他の方法
家族信託を利用して障害のある子供の財産管理を行なう方法
次に,信託を利用して障害のある子供のために財産を信託するという方法があります。
信託とは,大まかに言って,財産管理を依頼する委託者,財産管理を行なう受託者,財産管理の利益を受ける受益者が登場する制度になります。
例えば,親が障害のある子供のために信頼できる親族に財産管理を委ねた場合,親が委託者,信頼できる親族が受託者,障害のある子供が受益者ということになります。
家族信託制度を利用することのメリット
家族信託制度を利用することのデメリット
終わりに
以上,親の死後に障害ある子供の財産管理をする方法について解説を行いました。
通常の遺言書の作成時もそうですが,ご自身に元気がある時にはなかなか将来のための措置を採ることに消極的になってしまいます。
もっとも,これらの将来のための措置は早く行うことにデメリットは無いといえますので,思いついたときに行動されることをお勧めしています。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,今回ご紹介した親族に障害がある子がいる場合に限らず,信託,遺言書の作成,後見,任意後見を始めとした相続・将来の財産承継に関する知識・ノウハウを多数有しています。
本記事をご覧になり,もしご不明な点がございましたら,中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】夏期休業について
弊所では,令和元年8月13日(火)から8月16日(金)までの間は夏期休業のためお休みをいただいております。
メールでのお問い合わせにつきましては,内容を確認させていただきますが,返信が遅くなってしまうこともございますので,何卒ご容赦頂きますようお願い申し上げます。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
未婚で子供を出産した場合に強制執行を利用して養育費を回収する方法
前回の記事では,未婚で子供を出産した場合に子供の父親に養育費を支払わせるためには,養育費の合意を行う必要があることについて解説を行いました。
また,養育費の合意を行うに当たっての,その合意の書面化の必要性と書面化の具体的方法についても解説を行いました。
それでは,養育費の合意を行ったにもかかわらず,子供の父親が養育費を支払わない場合は,諦めなければいけないのでしょうか。
その答えとしては,養育費の回収をあきらめる必要はないというものになります。
中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,養育費の合意を行ったにもかかわらずこれを支払わない時に養育費を支払わせる方法を,今回の民事執行法の改正によりこれまで以上に養育費の回収をしやすくなった点も含めて,弁護士が解説を行います。
※なお,ここでも養育費を支払わない者を子の父親としておりますが,あくまで便宜上の設定にすぎませんのでご了承ください。
相手方が任意に支払わない場合は強制執行手続を行う
裁判所に対する強制執行申立手続の概要
まず,子供の父親が養育費の合意をしたにもかかわらず養育費の支払を行わない場合は,地方裁判所に対して強制執行の申立を行う必要があります。
この強制執行を行うことにより,養育費を任意に支払わない場合でも,子供の父親の同意なく財産を差し押さえた上で売却し,その売却代金から支払いを受けることができるようになります。
また,強制執行手続により預貯金や給料を差し押さえた場合は,預貯金や給料の全部または一部から支払いを受けることができるようになります。
この強制執行の申立てを行う裁判所ですが,子供の父親の住所地を管轄する(近くの)裁判所になります。
ですので,例えば,子供の父親が東京23区に居住している場合は,養育費の請求を行う未婚の母は,東京地方裁判所に強制執行の申立を行うことになります。
ただ,強制執行の対象を行うためには,差押えを行う財産を特定した上で,強制執行の申立書等の書面を用意しなければいけません。
強制執行を行うためには差押えの対象とする財産を特定する必要がある
前述の通り,強制執行の申立てを行うためには,養育費を請求する未婚の母の方で差押えの対象とする財産を特定する必要があります。
典型的な差押えができる財産としては,不動産,預金,給与,保険(解約返戻金であり,掛け捨ての保険ではダメです。)等があげられますので,養育費の請求を行う未婚の母は,子供の父親が有するこれらの財産のうち,どの財産を対象として強制執行を行うかを決めなければいけません。
なお,給料については,子供の父親が退職をした場合給与から回収を行うことはできなくなってしまいます。
ただ,その場合であっても退職金債権を差し押さえることできますので,子供の父親の勤務期間が長い職場であれば,退職される危険性は相対的に小さくなると言えるでしょう。
強制執行を行うためには差押えの対象とする財産の調査を,養育費を請求する側で行わなければならない
強制執行を行うためにはどこまで財産を特定する必要があるか
前述の通り,強制執行を行うためには,養育費を請求する未婚の母の側で,差押えの対象となる財産を特定するに足りる情報の調査を行う必要があります。
もっとも,これらの財産については,現在の法律では裁判所が探してくれるわけではないので,養育費を請求する未婚の母の方で差押えの準備を行う必要があります。
財産を特定できるだけの情報の具体例としては,不動産であれば対象不動産の所在,預金であれば金融機関名と支店,給料であれば勤務先,保険であれば保険会社になりますので,これらの情報を特定する必要があります。
差し押さえる財産がわからない場合の手段について
① 決め打ちでの強制執行の申立て
子供の父親の財産の特定が難しい場合において,まずできることの一つとしては,決め打ちで銀行口座等を狙って強制執行の申立てをする方法があげられます。
例えば,子供の父親の自宅近くの金融機関の預金口座宛に強制執行の申立てを行う方法です。
ただ当然のことながら,対象となる財産が存在しない可能性もありますので,賭けになってしまうといえるでしょう。
② 財産開示手続について
次の方法としては,財産開示手続を利用する方法があげられます。
財産開示手続とは,裁判所が子供の父親に対して呼び出しを行った上で,現在保有している財産を開示するよう求める手続になります。
仮に子供の父親が裁判所の求めに対し出頭を拒絶した場合は,裁判所の判断により過料の制裁が課されることになります。
ただ,財産開示手続を行ったにもかかわらず子供の父親が出頭をしなかったとしても,過料の制裁が課されないこともありますので,必ずしも実効性が高い手続とは言えません。
弁護士であれば,調停調書や審判がある場合メガバンクの預金は全店照会が可能
養育費の請求を行うためには請求を行う側で特定をする必要がありますが,その調査は容易ではありません。
もっとも,メガバンクの預金に限られますが,弁護士であれば弁護士会照会という手続を使うことにより,父親が持つ銀行口座の調査を行うことができます。
弁護士会照会を行うことにより,銀行側が子供の父親の有している口座を回答しますので,養育費の請求を行う母側は,回答された口座に対し差し押さえをすることが可能になります。
このように,養育費の確実な回収を狙うためにも,養育費(債権)回収に強い弁護士に依頼するメリットがあるといえます。
3.民事執行法の改正により子供の父親の財産調査が容易になった
既に述べた通り,強制執行を行うためには,子供の父親の財産調査を行う必要があるところ,父親の財産がわからない場合は,強制執行を行うことが難しいという問題がありました。
このような養育費の回収が難しいという現状を踏まえて,令和元年5月10日に,民事執行法が改正されました。
改正民事執行法では,以下の制度が新設され養育費の回収が容易になっています。
なお,改正法の施行はまだされていませんが,公布の日から政令で定める1年以内とされていることから,令和2年の4月頃までには,今後施行がなされる予定です。
金融機関に対し,預金口座や証券口座の有無を開示するよう求められるようになった
前述の通り,強制執行をするためには,銀行預金であれば支店まで特定する必要がありました。
しかし,今回の改正では,裁判所が金融機関(銀行,信用金庫,証券会社等)に対し預金口座や証券口座の有無を照会できるようになりました。
この制度の新設により,メガバンクに対する弁護士会照会によって従前なされていた口座の調査以上の調査が,裁判所を介してできるようになりました。
今回の法改正では,メガバンク以外の金融機関に対して照会ができるようになったということが大きな変更点と言えるでしょう。
市役所や年金機構に対し,給与支払者(勤務先)の情報を開示するよう求められるようになった
次に,今回の改正により,財産開示手続を経た後にはなりますが,裁判所が市区町村や年金機構に対し給与支払者(勤務先)の情報を確認できることになりました。
給与所得者の場合,住民税が特別徴収(給与から天引き)されることがあるため,市区町村は勤務先を把握していることがあります。
また,厚生年金に加入している場合は年金機構が勤務先を把握しています。
そのため,裁判所が市区町村等に対し照会を行うことにより,子の父親の現在の勤務先が判明し給料の差押えが可能になってくるのです。
今回の法改正によって,子供の父親がサラリーマンである場合は,今後は給料から養育費の回収をすることが容易になります。
登記所に対し,不動産の情報を開示するよう求められることになった
最後に,財産開示手続を経た後に,裁判所が登記所に対し対象者の不動産情報の照会をできるようになりました。
不動産の登記は誰でも閲覧・取得することができるため,法改正前も,子供の父親の住所地の登記等を調べることは可能でした。
もっとも,自宅以外の不動産に関しては,相手方がどこの不動産を保有しているかを知ることは困難でした。
今回の改正により,登記所に対して情報開示が可能になるため,例えば,子供の父親が不動産を隠し持っていた場合において,養育費の回収をすることがより容易になりました。
4.終わりに
以上,養育費の合意を行ったにもかかわらず,子供の父親が養育費を支払わない場合において回収する方法を解説しました。
従前は養育費を支払わないケースも多かったですが,法改正により,養育費を支払わない場合は強制的にこれを回収ができるようになりました。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,養育費の不払いを含む離婚・男女問題を重点分野としております。
養育費を含む離婚男女問題に関する問題でお悩みの方は,中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
未婚で子供を出産した場合に父親に養育費を支払わせる方法
中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所では,
「妊娠をしたものの事情があり,未婚で子供を出産した。けれども,将来養育費が支払われることが心配。」
「未婚で子供を出産し,出産当初は子の父親は養育費を支払っていたが,ある日を境に養育費が支払われなくなった」
というご相談をいただくことがございます。
未婚で出産をした場合であっても,子の父親から養育費を支払いやすくする方法,または,養育費を支払わせる方法は存在します。
養育費は子供のための権利ですので,子の父親にはしっかりと養育費を支払って欲しいところです。
それでは,子供の父親に対し養育費を支払ってもらうためにはどのような方法があるのでしょうか。
中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,未婚で子供を出産した場合に,子の父親に対し養育費を支払わせる方法について解説を行います。
なお,本ページでは養育費の合意ができていない場合の前提知識やまず行うべき方法を解説し,次回以降の記事では,養育費の合意ができているが支払わない場合の対処法について解説していきます。
▼養育費の合意ができているが支払わない場合の対処法はこちらをご参照ください。
※ここでは養育費を支払わない者を子の父親としておりますが,あくまで便宜上の設定にすぎませんのでご了承ください。
養育費の合意ができていない場合における前提知識とまずすべきことと
養育費発生の前提として父親と子供との間に法律上の親子関係が必要になる
まず,未婚であったとしても父親と子供との間に法律上の親子関係があれば,子の父親に対し養育費を請求することは可能です。
逆を言えば,生物学上の親子関係が生じていたとしても,法律上の親子関係が生じなければ養育費は発生しません。
この法律上の親子関係についてですが,法律上の親子関係が生じるためには,父と子の関係であれば,父が子を認知をすることが必要になります。
したがって,認知がなされている場合は,まずは子の父親との間で認知をするようにしましょう。
子の父親が認知をすることを認めている場合は,子の父親に認知届への記入を依頼し役所に届出を行うことになります。
他方で,子の父親の認知が見込めない場合であっても,認知をあきらめる必要はなく強制認知という手続による認知も可能です。
弁護士に依頼をした場合,認知から養育費の合意までベストな方法で解決をすることが可能ですので,お気軽にお問い合わせください。
養育費の合意は書面で行うことが大事
既に述べた通り,法律上の親子関係が生じていれば養育費の請求が可能です。
まず,養育費の具体的な金額は,基本は双方の収入,及び,子の年齢によって決まります。
養育費の金額は,養育費算定表という表がありますので,この表を参考に具体的な養育費がいくらかを計算しましょう。
具体的な金額が把握できた場合は,その内容を書面に残します。
仮に書面で合意内容の記録を残さないと,後に養育費の金額がいくらであるかについて争われてしまうからです。
次に,養育費の金額について相手方と合意をすることができたら,公正証書という書面で残すことをお勧めします。
なぜならば,この公正証書は,強制執行認諾文言という,仮に子の父親が養育費を支払わなかった場合であっても,直ちに強制執行ができる旨の条項を設けることにより,強制執行が直ちにできるからです。
ここで,強制執行とは,相手方が任意に履行をしない場合に回収をする手続です。
例えば,仮に子の父親が養育費を支払わない場合は,子の父親の給料や預金債権,不動産等の財産を差し押さえることによって養育費を回収することができます。
そして,仮に,給料債権を差し押さえた場合は,子の父親の勤務先に養育費を支払っていないことがばれてしまいます。
そのため,子の父親としては,養育費を支払わないとリスクが大きくなるため,公正証書を作成しない場合と比べて養育費を支払う可能性が上がると言えるでしょう。
子の父親が養育費の合意及び書面化に応じなくても解決策は存在する
養育費を定めるに当たっては合意内容を書面化することが大事といいましたが,子の父親が養育費の合意内容の書面化に応じない場合であっても,問題ありません。
その場合,家庭裁判所に対し養育費の調停を申立て,その結果調停が成立すれば調停調書という形で書面化がなされます。
更に,調停調書が存在する場合のメリットとしては,合意内容が書面化されるだけではなく,公正証書と同じく養育費が支払われなかった場合に,強制執行が可能という点もあります。
他方で,デメリットとしては,調停の成立のために時間を要するということや,手続のために法的知識が必要であること及び場合によっては交渉が必要になるということです。
調停の手続についてはご自身で進めることも不可能ではありませんが,経験を有する弁護士に依頼をすることがより確実であると言えます。
養育費の獲得に不安な方は弁護士にご相談ください。
終わりに
以上,まずは本ページでは,未婚で子供を出産したが,子の父親と養育費の合意ができていない場合において,まずどのような手続を行うべきであるかについて解説を行いました。
記事の冒頭でも言及したとおり,養育費は子供のための権利ですので十分にこれが支払われるべきですが,そのためには手続及び法の内容について十分な知識を取得し準備を行う事が必要不可欠になってきます。
子供の養育費を含めた離婚・子供・男女関係については,東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では重点分野としてこれを取り扱っております。
子供の養育費に関してご不明な点がありましたら,中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所までお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
知らないうちに(勝手に)養子縁組がされた場合にどのように争えばよいか
中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所では,
「親族が亡くなったので,遺産分割をするために戸籍を調べたら知らないうちに養子縁組がなされていた。」
との相続に関連する養子縁組に関するご相談をいただくことがよくございます。
このような事態が生じることは珍しくなく,相続のご相談に関連して弊所にご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
それでは,このように知らないうち(勝手)に養子縁組がなされた場合,相続にどのように影響があるのでしょうか。
また,このように知らないうちに養子縁組がなされそれが納得できない場合,どのように争っていけばよいのでしょうか。
中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,知らないうちに養子縁組がなされる背景や,養子縁組の効力の争い方について解説を行います。
相続対策のために養子縁組が利用される背景
養子縁組を行うことによって,養親と養子との間に法律上の親子関係が生じます。
そして,法律上の親子関係が生じると,以下のような効果が生じるため,相続にあたり養子縁組が利用されることがあります。
養子縁組によって法定相続人となるべき人が変わる
相続法では,配偶者の他に相続人となる親族の順番が決められています。
配偶者は必ず相続人になりますが,それ以外には
①子供
②親
③兄弟
の順番でこれらの者が相続人になります。
配偶者がいない場合は,これらの者のみが相続人になります。
例えば,独身で子供がおらず,また親がすでに亡くなっていた被相続人の場合は,被相続人の兄弟が相続人になります。
しかし,例えば上記被相続人と第三者が養子縁組をした場合,当該第三者は当該配偶者の子供になるため,被相続人の兄弟は相続人ではなくなります。
したがって,当該第三者が遺産をすべて取得することになります。
養子縁組によって法定相続割合が変わる
例えば,被相続人の配偶者が死亡して,子供が三人いる場合,子供は各3分の1の割合で相続分を有することになります。
しかし,例えば,被相続人が長男の子供(被相続人の孫)と養子縁組をした場合,被相続人には子が4人いることになります。
したがって,養子縁組をすることによって,長男とその子供は各4分の1(長男側は合計2分の1),その他の被相続人の子は各4分の1のみ相続できることになります。
養子縁組によって遺留分割合が変わる
養子縁組をすることによって法定相続割合が変わることは既に述べた通りです。
そして,養子縁組をした場合は遺留分割合も変わることもあります。
遺留分割合は,総体的遺留分に法定相続割合を乗じて算出されます。
例えば,子供が2人いる場合は,各子どもの遺留分割合は,遺産の4分の1(総体的遺留分割合×法定相続割合)になります。
このように,法定相続割合と遺留分が関連するため,法定相続割合が変わる結果,遺留分割合も変わってくるのです。
例えば,子供2人の相続の場合において,被相続人が養子縁組を行った場合,子供が3人になるので,各相続人の遺留分割合は各6分の1になります。
上記の通り,養子縁組によって遺留分割合を減らすことができるため,遺留分対策のために養子縁組を利用することがあります。
養子縁組によって相続税の基礎控除が変わる
相続税には基礎控除というものがあり,基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しません。
基礎控除額は,3000万円+相続人の数×600万円になります。
また,生命保険についても非課税となる限度額が
500万円×相続人の数と決まっています。
養子縁組がなされた場合,法定相続人の数が増えることになりますので,この基礎控除額や非課税限度額が増えることになります。
但し,相続税法上,養子の数は,実子がいる場合は1名まで,実子がいない場合は2名までが決められていますので,この点に注意が必要です。
知らない間(勝手)に出された養子縁組の効力を争うためにはどうしたらよいか
知らない間(勝手)に養子縁組がなされる背景は以上の通りですが,それでは知らない間に出された養子縁組の効力を争うためにはどのようにすればよいのでしょうか。
まずは,その前提として,養子縁組が無効になるのはどのような場合でしょうか。
養子縁組が無効になるのはどのような場合か
民法では,養子縁組が無効になる場合について規定しています。民法802条によれば以下の通りです。
民法第802条
縁組は,次に掲げる場合に限り,無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし,その届出が第789条において準用する第739条2項に定める方式を欠くだけであるときは,縁組は,そのためにその効力を妨げられない。
つまり,当事者間に養子縁組をする意思が無い場合,または,養子縁組の届出をする意思が無い場合に養子縁組が無効になります。
例えば,養子縁組をするつもりが無いのに勝手に出されてしまう場合や,養子縁組をする意思はあるものの,まだ届出をするつもりはなかったのに勝手に出されてしまう場合がこれらに該当します。
なお,勝手に養親組届が提出されるのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが,勝手に養子縁組届を出すことはありえます。
なぜならば,戸籍の窓口ではその養子縁組が真意に沿ってなされたかを審査することはできないからです。
養子縁組を争うためにはどのような手続をとるべきか
それでは,縁組意思または届出意思が欠けていることを理由に養子縁組を争う場合,どのような手続をとるのでしょうか。
養子縁組の効力を争う場合は,家庭裁判所に対し,調停の申立て,または,人事訴訟を提起する必要があります。
この調停と訴訟の関係ですが,家事事件手続法では,調停前置と呼ばれる訴訟よりも先に調停を行わないとならないという仕組みがあるので,人事訴訟に先立って調停を行わなければいけません。
もっとも,養親または養子が死亡している場合は,調停後になされる合意に相当する審判ができないため(家事事件手続法277条第1項),調停を行う実益がありません。
そのため,養親又は養子が死亡している場合は,調停の申立てをせずに訴訟提起を行うことになります。
養子縁組無効確認裁判手続後の流れ及び注意点
家庭裁判所に対し訴訟提起を行った後,当事者間で,養子縁組が無効であったか否かについて争っていくことになります。
この場合の注意点としては,離婚等の裁判であれば和解が可能になりますが,養子縁組の無効を前提とする場合,裁判を通じた和解による解決ができないという点です。
訴訟手続をするにあたっては,上記の点を踏まえて手続を進めていく必要があります。
養子縁組の効力を争うための証拠収集の方法
最後に,養子縁組の無効を争っていくためには,どのような証拠を収集すべきでしょうか。
この点について,まずは,戸籍届書の記載事項証明書を取得する必要があります。戸籍謄本とは異なり,記載事項証明書には養親の署名や押印欄がありますので,まずは資料を取り寄せて,本人の署名・押印であるかを確認します。
その上で,養親のカルテ,介護記録,介護認定資料等の医療情報を収集します。カルテ等を確認した上で,養親が養子縁組の内容を理解できる状態であったかという点の分析を行います。
更に,養親と養子の関係がわかる資料を取得します。養子縁組を行うにあたっては,養親と養子の関係が重要になりますので,当事者の関係の親疎も確認しなければいけません。
これらの資料を基に,養親縁組の効力を争っていくことになります。
終わりに
以上,知らない間(勝手)に,養子縁組がなされた場合の対処方法について解説を行いました。
養子縁組の無効を争うケースにおいては,どのような手続をとるかという点や,縁組の無効を争うためのノウハウが重要になってきます。
弊所では,実際にご依頼後に養子縁組無効確認訴訟提起を行い,その結果訴訟提起前よりもご依頼者様に有利な内容で問題が解決した実績もございます。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,養子縁組の無効を含む相続分野を重点分野としております。
養子縁組の効力についてご不明点等ございましたら中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】ゴールデンウィーク中の営業について
弊所では,4月27日(土)から5月6日(月)までの間お休みをいただきます。
上記休業期間であってもメールやお問い合わせの確認は致しますので,お問い合わせがございましたらこちらよりお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
『建設会社向け』注文者・発注者(注文・発注・元請会社)の建設工事代金未払・破産の場合に,建設工事代金を回収するためにはどうしたらよいか
中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所では,建設会社の方から,
「工事の発注を受けたので工事を完了したが,建設工事代金の支払いがなされない。」
「元請会社から建物の建築を依頼されたため下請会社として工事を行ったところ,元請会社が破産をしてしまったがどうしたらよいか。」
「注文会社から内装工事を依頼され工事を進めたが,注文会社が倒産をしてしまったが建設工事代金を回収できるか。」
このようなご相談をいただくことがございます。
本ページでは,工事の注文を行った側を注文会社,建設会社側を請負人として,工事の注文会社から建設工事代金の未払がある場合や注文会社が破産をした場合にどのように債権回収を行えばよいかについて弁護士が解説を行います。
★ なお,債権回収に関連する情報は,下記ページもご参照ください。
注文会社(元請会社)から依頼された工事が完了したが建設工事代金の支払がなされない場合
建設工事が完了したにもかかわらず注文会社から建設工事代金が支払わないことがありますが,注文会社(元請会社)から建設工事代金が支払われない理由は様々です。
例えば,注文会社(元請会社)から建設工事代金が支払われない理由としては以下のものがあげられます。
①注文会社に支払原資がない・資金繰りが苦しいので支払うことができない。
②仕事を完成させたが瑕疵(ダメ工事)がある。
③注文に応じて追加変更工事を行ったが,注文会社が理由をつけて建設工事代金を支払わない。
このような場合,上記注文会社の反論に応じてどのように建設工事代金を回収するかを決める必要があります。
注文会社に支払原資がない,注文会社の資金繰りが苦しい場合
注文会社に単に支払原資がない場合,基本的には,注文会社が建設工事代金の支払を拒める法律上の理由はないと言えるでしょう。
したがって,注文会社が建設工事代金の支払を拒絶した場合,内容証明郵便を発送して建設工事代金の支払を求めた上で,裁判手続を行うことも検討したほうが良いです。
【内容証明郵便発送による建設工事代金の請求】
内容証明郵便を送る場合,建設工事の内容,建設工事の支払金額や支払先の口座,及び,支払がなされない場合は法的措置をとること等を明記することを忘れないようにしましょう。
なお,内容証明郵便を送るにあたっては,会社名義で送る場合と弁護士名義で送る場合がありますが,弁護士名義で送ることにより,注文会社に対して本気度を伝えることができます。
【裁判手続による建設工事代金の請求】
仮に,内容証明郵便を発送してもなお建設工事代金の支払を拒絶する場合は裁判手続に進むことになります。
裁判手続を行うにあたっては,訴訟前に注文会社の財産処分を制限する仮差押という手続があります。
例えば,注文会社の預金や不動産の仮差押を行うことによって,裁判が行われている最中に注文会社が財産を処分し,隠してしまうという事態を防ぐことができます。
債権回収に当たっては,財産確保が重要ですので,可能であればこの仮差押を行った方が良いと思います。
なお,別のメリットとしては,仮差押をすることによって,相手方が任意の支払に応じることもあるという点があげられます。
そして,注文会社に対する内容証明郵便の発送や仮差押を行ったにもかかわらず,建設工事代金の支払を行わない場合は,訴訟提起を行うことになります。
訴訟提起後,判決が出てもなお相手方が建設工事代金の支払に応じない場合は,強制執行を行い建設工事代金の回収を行うことになります。
仕事に瑕疵(ダメ工事)がある,追加変更工事の報酬について争いがある場合
これらの場合は,注文会社の建設工事の瑕疵(ダメ工事)の主張や追加変更工事における報酬の合意に関する主張が法律上正当であるかを確認する必要があります。
仕事に瑕疵(ダメ工事)がある場合や,追加変更工事がなされた場合における報酬額については,法律上様々な論点がありますので,この場合における対応策については別記事において解説を行います。
ただ,これらの反論がなされた場合であっても,仕事が一応の工程を終了したのであれば報酬を請求することは原則として可能です。
したがって,注文会社に対して建設工事代金の支払請求を行う場合は,内容証明郵便の発送等,前述と同様の手続を進めていくことになります。
注文会社が破産をした場合
上記では,注文会社が建設工事代金を任意に支払わない場合のみを念頭において解説を行いましたが,注文会社が破産をした場合はどのような手続をとるべきなのでしょうか。
以下では,注文会社が破産をした場合において,
①どのような手続が進み,建設請負契約はどのようになるのか
②その場合において建設工事代金を回収するためにはどのような手段が存在するのか
について言及を行います。
1 注文会社(注文会社)が破産した場合はどのような手続となり,建設請負契約はどうなるか
まず,注文会社の破産手続が開始されることになると,破産管財人が選任されます。
破産管財人には,弁護士が選任され,この破産管財人は,破産した注文会社に代わって財産の管理・処分を行うことになります。
そして,破産手続が開始されたとしても,既に締結した請負契約自体は破産手続の結果当然に消滅するわけではなく,建設請負契約自体は残ることになります。
ただ,破産の結果建設工事代金を受け取れない可能性が存在するにもかかわらず,工事を続けなければいけないのは酷ですので,請負人側が建設請負契約を解除することが認められています。
また,破産法上,破産管財人も請負契約を解除することが可能となっています。
このように,建設請負契約自体は破産手続が開始された後であっても,契約自体は継続することになりますが,実務上は,請負契約を実現させることによるメリットが大きくないことから,請負契約が解除されることが多くなります。
請負契約が解除された場合は,今までに工事が完了した出来高部分を算定した上で,破産管財人との間で,既に注文会社が支払っている前払金と精算をすることになりますが,工事の出来高がどの程度であるかによってその後の対応は変わってきます。
【出来高が前払金よりも大きい場合】
前払金よりも完成部分の出来高が多い場合,つまり,注文会社から既に受領した代金よりも完成した工事の程度が進んでいる場合は,請負人は注文会社に対して工事代金の請求をすることが可能になります。
但し,当該報酬請求権は破産手続において請求できる権利に過ぎず,破産者の財産から弁済されるにすぎないので,回収の見込みは低いと言わざるを得ません。
したがって,回収の期待可能性は低いことを前提にした上で,回収をするためには,以下で記載の通り商事留置権を主張する等の措置を検討しなければいけません。
【出来高が前払金よりも小さい場合】
この場合は,完成した仕事の程度よりも前払金の方が大きい,つまり,注文会社から既に受領した代金よりも完成した工事の程度が進んでいない場合は,請負人は注文会社(破産管財人)に対し支払を行う必要がでてきます。
但し,これはあくまで出来高が前払金よりも小さいことが確定したことが前提になります。
そもそもの話として,建設工事の出来高の割合がどの程度であるかということが争点になりますので,破産管財人からの前払金返還請求に対しては,この点を十分に検討したうえで交渉をすることが必要になります。
2 請負人が投入した金銭・労働をできる限り回収するためにはどうしたらよいか
注文会社が破産をした場合,請負人側が報酬代金を回収することは難しい側面があることは否定できません。
そうだとしても,既に投入した金銭や労務をできる限り回収するためには,以下の方法が考えられます。
孫請業者が元請業者と直接契約を締結する方法
まず,請負人が孫請業者,注文会社が下請業者である場合に注文会社である下請業者が破産した場合,孫請業者である請負人は,元請業者と直接契約を締結することが考えられます。
というのも,元請業者としては,下請業者が破産をしてしまったことにより工事の完成がストップしてしまい,施主との関係で債務不履行が生じることから,工事を続行したいと考えることがあるからです。
但し,元請業者に対して契約を締結することを強制することはできないため,請負人としては,あくまで契約締結の交渉を行うというスタンスで進めることになります。
商事留置権を主張する方法
商事留置権とは,簡単に言えば,事業によって生じた債権を有する場合に代金の支払いがなされるまで債務者の所有物の引き渡しを拒める権利のことを言います。
例えば,自社の倉庫に取引先の商品が存在する場合において,取引先の代金不払いがある場合には,取引先からの商品の引渡請求が拒むことができます。
この商事留置権に基づき,建設工事代金の未払を理由に建設中の建物を留置し,注文会社に対し,間接的に代金の支払を求めていくことになります。
ただ,商事留置権が認められるための要件や効果については議論があるため,建設工事代金の未払の際に商事留置権が成立するかについては,難しい論点を検討しなければなりません。
そのため,商事留置権の主張を行う場合は,弁護士にご相談をされることをお勧めいたします。
終わりに
以上,注文会社・元請会社の建設工事代金未払・破産の場合に,建設工事代金を回収する方法について解説を行いました。
建設工事代金の回収をはじめとする債権回収においては,スピードと回収するための戦略が重要になってきます。
また,建設工事代金の回収については,請負契約に関する知識も当然必要になります。
東京中野区所在の吉口総合法律事務所では,建設工事代金の回収をはじめとする債権回収を重点分野としております。
建設工事代金の回収についてご不明点等ございましたら中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所までお気軽にご連絡ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
新たに外国人を雇用するために知っておく知識(外国人技能実習制度・特定技能制度について)
日本の労働者人口減少による外国人労働力の確保が問題となっています。
このような課題から,入管法が改正され,平成31年4月より改正入管法が施行されます。そこでは新たな在留資格として「特定技能」が設けられています。
この「特定技能」とは別に,平成29年11月に施行された技能実習法に基づき外国人技能実習制度が存在するのですが,上記「特定技能」との違いはどのような点にあるのでしょうか。
本コラムでは,上記制度の違いについて,東京都中野区所在の企業法務を扱う弁護士が解説を行いたいと思います。
▼:特定技能に関するよくある質問については,こちらをご覧ください。
▼:外国人労働者雇用の際の一般的な注意点については,こちらをご覧ください。
なお,特定技能制度については,まだ改正入管法が未施行であるため,法務省で交付されている資料に基づく解説になることにご留意ください。
外国人技能実習制度と特定技能制度の目的の違い
外国人技能実習制度の目的
外国人技能実習制度とは,「人材育成を通じた開発途上地域等への技能,技術又は知識の移転による国際協力をすること」(外国人技能実習法第1条)を目的とする制度になります。
要は,外国人技能実習制度は,外国人に対する技能移転を目的とする制度になります。
この目的からもわかる通り,外国人技能実習制度は労働力の確保を目的とするものはありません。
むしろ,外国人技能実習法では,技能実習が,労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています(法第3条2項)。
「特定技能」制度の目的
これに対し,特定技能制度の目的は,正に外国人労働者の確保による労働力不足の解消のために制定されたものになります。
したがって,外国人技能実習法と特定技能制度では,労働力の確保を目的とするか否かという点で目的が大きく異なると言えます。
このような目的の違いから,外国人技能実習制度では転籍・転職等が原則として認められていないのに対し,「特定技能」では,転籍・転職等が可能になっています。
外国人技能実習制度と特定技能制度のそれぞれの仕組み
外国人技能実習制度の仕組みについて
外国人技能実習制度においては,
①企業単独型
②監理団体型
の2種類があります。①の企業単独型については,例えば,外国企業と親子関係にある会社間において,当該会社に対し技能移転を行うため外国人労働者の受け入れを行う場合がこれにあたります。
もっとも,外国企業と親子関係にあるという例からもわかる通り,この類型はある程度の規模の会社であることが想定されます。
そのため,外国人技能実習においては,次の監理団体型を利用する場合の方が多いのではないでしょうか。
②の監理団体型ですが,これは,実際に外国人の受け入れを行う「実習実施者」の他に,「監理団体」という,外国人技能実施制度が目的に沿って行われているかを確認する団体が存在する類型になります。
外国人技能実習において,多くはこの類型を利用するのではないでしょうか。
この類型では,外国人労働者の受け入れに当たり,概ね以下の流れで手続が進んでいきます。
①監理団体による指導・助言の下実習実施者が実習計画を提出した後,
②外国人技能実習機構が実習計画の審査・認定を行った後,実習実施者に認定通知書を交付し,
③監理団体が認定通知書を添付して入管に対し在留資格認定の申請を行い
④入管から監理団体が在留資格認定書の交付を受け,技能実習生が送付を受けた当該認定書と査証を取得し入国する。
⑤入国後は,技能実習計画に従って技能実習を行う。
外国人技能実習制度の場合,概ね上記流れで手続が進んでいくことになります。
特定技能制度の仕組みについて
新たに創設された特定技能制度の場合,
①特定技能1号
②特定技能2号
という在留資格がそれぞれ設けられています。
前者の特定技能1号というのは,介護やビルクリーニング,建設等の14分野の産業について,外国人がこれらの就労を目的として日本に在留することができる資格になります。
在留期間としては,最長5年になり,在留資格の取得に当たり生活や業務に必要な日本語能力が必要になります。
後者の特定技能2号というのは,同1号を発展させたものであり,同1号よりも更に熟練した技能を有する者が取得できる在留資格になります。
特定技能制度の場合は,外国人の他,外国人の雇用先となる「受入れ機関」,「受入れ機関」が行う外国人の支援計画に基づく支援の援助を行う「登録支援機関」が存在します。
そして,「受入れ機関」である企業が外国人労働者の受け入れを行うに当たっては,外国から受け入れるのか,国内から受け入れるのかにもよって多少異なりますが,
①当該外国人との特定技能雇用契約の締結
②(受入れ機関である企業が外国人の支援ができない場合)登録支援機関との委託契約の締結
③受入れ機関による特定技能外国人支援計画の作成
④在留資格認定・在留資格変更許可の申請
という流れで進んでいくことになります。
外国人技能実習制度及び特定技能制度の注意点
外国人技能実習制度の注意点について
外国人技能実習制度のうち,特に利用されるのが監理団体型であるため,監理団体型における注意について論述します。
【監理団体における注意点】
監理団体が監理事業を行うためには,主務官庁の許可が必要であり,許可のための要件がそれぞれ定められています。
例えば,許可要件の一つとして「監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること」が必要です。
上記要件を具体化するために,外国人技能実習規則では監理業務の実施の基準を設けているのですが,監理団体を運営するためには,前期基準を守らなければなりません。
このような基準を守らない場合,許可の取消等がなされてしまうため,注意が必要です。
【実習実施者の注意点】
外国人技能実習制度において,技能実習生との間で雇用契約を締結するのは,実習実施者になります。
したがって,技能実習生との間の雇用契約の締結においては,労働基準法等労働法規に従う必要があります。
また,実習実施者は,技能実習計画に従った技能実習を行う必要があります。
技能実習計画に従わない技能実習を行った場合,技能実習計画が取り消され,技能実習ができなくなってしまうこともありますので,技能実習計画に従った技能実習を行うよう注意しましょう。
特定技能制度の注意点について
特定技能制度を利用して外国人と雇用契約を締結しますが,この雇用契約は,外国人であるからと言って報酬額を不当に安くすることはできません。
雇用契約についても労働基準法の適用がありますので,これらの法令を遵守することが必要になります。
終わりに
以上,外国人技能実習制度及び特定技能制度について解説を致しました。
人手不足のために外国人を労働者として雇い入れる場合は,まずは制度を理解するとともに,これらに対する法規制について理解を深める必要があります。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では,外国人技能実習制度や特定技能制度を含めた労働問題・企業法務問題についてご相談を随時受け付けております。
外国人技能実習制度や特定技能制度についてご不明な点がおありの方は,当ホームページのお問い合わせフォームまたは事務所までお気軽にお電話ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
不貞相手に対する不貞慰謝料請求に対する最高裁判例の紹介
不貞行為を行った不貞相手に対する損害賠償請求に関して,本日(平成31年2月19日),第三小法廷にて最高裁判決が出ました(以下,本コラムでは,今回の判決を「不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例」といいます。)。
この判例については,不貞相手に対する不貞慰謝料というある意味では身近な問題ということもあり,ニュースにおいても取り上げられているようです。
それでは,今回の不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例は,不貞相手に対する不貞慰謝料についてどのようなことを判示したものであり,今後どのような影響があるのでしょうか。
まだ判決が出たばかりであり,判例解説等が出されていないことから暫定的な解説になりますが,中野区で無料相談対応の吉口総合法律事務所作成の本コラムでは,上記不貞相手に対する不貞慰謝料請求に関する判決について弁護士が解説を致します。
今回の不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例の事案と判示事項
最高裁判例の事案
今回判決がなされた不貞相手に対する不貞慰謝料請求に関する最高裁判例において問題となった事案の概略は以下の通りです。
※最高裁判例の事案のみを参考にしており,原判決の事実関係についてはまだ未確認になります。
- 不倫を行った妻は,不倫相手と平成20年12月頃知り合い,平成21年6月以降不貞行為に及ぶようになった。
- 夫は,平成22年5月頃,妻が不倫を行ったことを知り,妻と不倫相手との不貞は解消された。
- 夫と妻は,平成27年2月に離婚をした。
- 夫は,妻の不倫相手に対し慰謝料請求を行った。
最高裁判例の判示事項
上記事案について,不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例は,以下のように判示しています。
※太文字や文字の色等を,適宜修正しています。
「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことは無いと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情が無い限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」
不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例を理解する上での前提知識
まず,不貞行為に基づく損害賠償請求を行うに当たって理解する必要がある事項があります。
それは,
①離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)
②離婚の原因となった個々の行為に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)
とそれぞれ種類があることです。
①については,何らかの有責行為によって離婚をするに至ってしまったことに対して発生する慰謝料になります。
他方で,後者の②については,離婚の原因となった不貞行為や暴力行為そのものに対して発生する慰謝料になります。
そして,本件の判例は,第三者に対して,①離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料請求ができるか否かが問題となった事案において,この点について主として判断したものになります。
この点について,本件の判例は,不貞相手が離婚をさせたことについて責任を負うのは,不貞行為のみではなく,不貞相手が離婚をさせるのもやむを得ないと評価できる行為を行った等特段の事情がある場合に限定しています。
不貞相手に対する不貞慰謝料に関する最高裁判例に対する今後の影響
詳しくは判例評釈を待つ必要がありますが,本判決は,不貞行為を行った不貞相手に対し,①離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料を求めることができる条件を絞ったものにすぎず,②の離婚の原因となった個々の行為に対する慰謝料について新たに判断しているわけではないと考えられます。
したがって,本判決によっても,不貞相手に対し,②離婚の原因となった個々の行為に対する慰謝料を請求することについては,従前どおり可能であると思われます。
この点について,一部のニュースではあたかも不貞相手に対する請求ができないように読み取れるものもありますが,不貞相手への慰謝料請求ができなくなったと判断することは早計でしょう。
ただ,今後不貞相手に対し慰謝料請求を行う場合は,消滅時効に気を付ける必要はあると思います。
原判決の事実関係を確認する必要がありますが,おそらく,本件は消滅時効の関係で,不貞相手に対し,①の離婚が成立するに至ったことに対する慰謝料を請求したものと思われます。
というのも,損害賠償請求を行うためには,損害及び加害者を知ってから3年以内にこれを行う必要があります。
そして,本件では,妻との不貞行為を知ってから3年が経過していたが,離婚をしてからは3年が経過していなかった場合に不貞相手に対し慰謝料請求をしたという事案なのではないでしょうか。
今後,本判例と同様の場面では,消滅時効の関係で,不貞相手に対して不貞行為に基づく損害賠償請求を行うことが制限される傾向になるかもしれません。
終わりに
以上,不貞相手に対する不貞慰謝料に関する平成31年2月19日最高裁判決を紹介しました。
同判決がまだ出たばかりであり,また,その解釈も確定しているわけではないため,今後の判例解説や裁判例の集積が待たれるところです。
中野区で相続無料相談対応の吉口総合法律事務所では,不貞慰謝料請求を行う側,及び,不貞慰謝料の請求をされた側のいずれのご相談もお受けしておりますので,お気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
遺産預金の使い込みがある場合における相手方の反論と返還請求の可否
中野区で相続無料法律相談対応の吉口総合法律事務所では,相続に関するご相談を多数受けております。
その中でもご相談内容として多いものは,”遺産である預金の無断引き出し・使い込み”の問題です。
被相続人である親や兄弟が亡くなったため,預金残高を確認したところ想定以上に預金が少なかったため,「遺産である預金が引き出されたのではないか・・・?」と考えるに至ることが多いようです。
今回のコラムでは,遺産である預金が無断で引き出された(使い込まれた)場合において,遺産である預金を使い込まれた相続人は使い込んだ者に対して返還請求をすることができるか,そして,返還請求をするためにはどのような準備をすればよいか等について弁護士が解説を行います。
▼遺産である預貯金の使い込みの問題の解決事例は,こちらをご参照ください。
▼ご親族が生存・存命中の使い込みの問題については,こちらをご参照ください。
引き出された預金の返還請求が認められるか否かの判断要素
まず,前提として,被相続人である親や兄弟の遺産である預金が多数引き出されている場合において,他の相続人は遺産である預金を引き出した者に対して返還請求をすることができるのでしょうか。
この点についての回答は,「遺産である預金が無断で引き出された(使い込まれた)場合は,他の相続人は引き出したものに対し返還請求ができる。」というものになります。
民法上,不当利得返還請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権という権利が存在するため,相続人は同請求権に基づいて,遺産である預金を無断で引き出した者に対し,無断で引き出された(使い込まれた)預金の返還を求めることができます。
それでは,どのような事情が存在すれば,他の相続人は無断で引き出された(使い込まれた)預金の返還請求を行うことができるのでしょうか。
この点については,以下の通りになります。
被相続人である親や兄弟死亡前における預金の使い込み(使い込み)について
遺産である預金の無断引き出し・使い込みは,死亡前になされるパターンと死亡後になされるパターンが存在します。
死亡前における引出が,無断引き出し・使い込みにあたるというためには,「預金の引き出しが,被相続人である親や兄弟の意思に反するものである」と言えなければいけません。
そして,これは,遺産である預金を引き出された側が主張・立証する必要があります。つまり,仮に遺産である預金の引き出しが,被相続人である親や兄弟の意思に反することを立証できなければ,いかに疑わしい事情が存在したとしても,遺産である預金を引き出された(使い込まれた)と主張する側の返還請求が認められないことになります。
ただ,通常は被相続人である親や兄弟の意思が明確にわかる資料は存在しないことが多いです。
そのため,預金の引出頻度や,引き出された金額・時期,被相続人と引き出した者との関係,被相続人である親や兄弟の当時の身体状態・認知状態,被相続人の生活状況,相手方の使途の説明内容等の要素から,被相続人である親や兄弟の意思を推認していくことになります。
例えば,父親が寝たきりの重度の認知症の状態であり,施設に入所していた中,遺産である預金から多額の金銭が引き出された場合,お父様は当該出金を認識できず,また,通常高額な金銭を支出する必要性が乏しいため,「被相続人である親や兄弟の意思に反していた」と認定される可能性が高いと言えるでしょう。
また,例えば,母親が死亡する直前に,遺産である預金から多額の金銭が引き出されていた場合,このような場合もお母様が金銭を必要とする事情は通常ないことから,「被相続人である親や兄弟の意思に反していた」と認定される可能性が高いと言えるでしょう。
上記のような事例であれば比較的判断がつきやすいですが,判断が難しい事案は多数ありますので,早期に弁護士にご相談をいただけますと今後の見通しを説明しやすくなります。
被相続人である親や兄弟死亡後における預金の使い込み(使い込み)について
上記とは異なり,遺産である預金の無断引き出し・使い込みが死亡後になされるパターンも存在します。
このようなケースでは,既に被相続人である親や兄弟が亡くなっていることから,預金の無断引き出し・使い込みにあたるといえるためには,「預金の引き出しが相続人の意思に反するものである」と言えなければなりません。
この場合は,死亡前の引き出しとは異なり,被相続人ではなく,相続人の意思に反する引出か否かが基準になりますので争い方の構成が変わることになります。
遺産である預金が,無断で引き出されているか(使い込まれているか)否かを調べる(立証する)方法
既に述べた通り,遺産である預金が引き出された場合において,預金を引きだした者に対する返還請求が認められるためには,遺産である預金を引き出された側が,無断引き出し・使い込みにあたることを主張・立証する必要があります。
それでは,預金の無断引き出し・使い込みにあたると立証するためには,どのような資料が必要になるのでしょうか。
遺産である預金の使い込み(無断引き出し)額に関する資料について
まずは,前提として,引き出された預金額がいくらであるかを把握・立証する必要があります。
この点を立証するためには,預金通帳が残っているのであれば,預金通帳が資料になります。
また,預金通帳が残っていない場合もありますが,そのような場合であっても,相続人であれば,金融機関に対して取引履歴の照会を行うことができます。
金融機関にもよりますが,被相続人が死亡したことがわかる戸籍謄本や被相続人との関係がわかる戸籍を用意すれば,概ね10年分の預金の取引履歴を出してくれることが多いです。
被相続人が保有していた預金の口座番号等がわからない場合もありますが,その場合であっても金融機関に確認をするとデータが残っている範囲で預金口座の有無を教えてくれます。
なお,金融機関によっては,他の相続人の同意が無いこと等を理由として預金取引履歴の開示を拒否することが稀にありますが,以下の平成21年1月22日最高裁判決の通り,基本的には金融機関は取引履歴の開示を拒否することはできません。
「金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そして,預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」
弊所では取引履歴の取得からご依頼をいただくことも可能ですので,もし資料を取得できないとお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。
被相続人の身体状態・認知状態に関する資料について
次に,遺産である預金が無断で引き出された(使い込まれた)時点において,被相続人である親や兄弟の身体状態・認知状態が悪ければ悪いほど,遺産である預金の引き出しが被相続人の意思に反していたといいやすくなります。
というのも,一般的には,被相続人が元気な状態であれば,被相続人本人が預金を引き出したと言いやすくなり,また,被相続人本人が引き出した預金を使用していたと言える可能性が高まるからです。
したがって,遺産である預金を無断で引き出した(使い込んだ)者に対して返還請求をするためには,被相続人の状態を立証する資料を取得することが重要になってきます。
この被相続人の状態を立証するための資料としては,医師のカルテや看護記録,介護施設の日報,介護認定の際に作成される主治医意見書や認定調査票等があげられます。
これらの資料は,病院や介護施設,介護認定を受けていた市区町村等から取得できますが,病院等によっては開示を拒否する場合があります。
このような場合であっても,弁護士が介入することによって資料が開示されることもありますので,お困りの際はお問い合わせください。
遺産である預金の無断引き出し・使い込みが疑われる側が良く行う反論と対策
遺産である預金の無断引き出し・使い込みに関する資料を取得・確認した結果,遺産である預金を使い込んだと疑われるのであれば,不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,無断で引き出された(使い込まれた)金銭の返還請求を行うことになります。
その場合であっても,相手方からどのような反論がなされるかを予想したうえで対策を事前に練っておくことが有益です。
それでは,遺産である預金の無断引き出し・使い込みが疑われる相手方からは通常どのような反論がなされるのでしょうか。
被相続人死亡前の無断引き出し・使い込みに対する反論
【被相続人本人が預金を引き出したものであるという反論】
まず,相手方から,「被相続人本人が預金の引き出しを行ったのであって,自分は預金の引き出しを行っていない」という反論が想定されます。
このような反論がなされた場合,預金の引出場所や被相続人の状態から当該反論が不合理であることを主張・立証することが考えられます。
例えば,被相続人と無断引き出しが疑われる相続人の自宅が遠く離れているにもかかわらず,預金の引出場所の大半が,当該相続人の自宅の支店であった場合,当該相続人の主張は不合理であると言いやすくなるでしょう。
また,被相続人の足の状態が悪かった,認知症で引き出される状態ではなかった等の事情があった場合も,被相続人本人が預金を引き出していないことの一つの根拠になると言えます。
なお,預金が引き出された支店は,取引履歴に記載されている番号等から判明することがよくありますので,取引履歴を取得した場合は事前に確認をするとよいでしょう。
【引き出した預金は被相続人から贈与を受けたものであるという反論】
次に,「預金を引き出したのは被相続人本人ではなく自分であるが,引き出した預金は被相続人から贈与を受けた」という反論がありえます。
このような反論がなされた場合,被相続人の状態,贈与がなされた時点における被相続人と引出を行った相続人との関係や,贈与に関する経緯,引出しの態様・金額・頻度,贈与を裏付ける資料の有無から,贈与が存在しなかったことを主張立証することが考えられます。
例えば,被相続人と引出を行った相続人との関係が悪化しており,贈与がなされるような状況ではなかったにもかかわらず,高額な金銭が引き出されていた場合,贈与が不自然であり贈与が不合理であると言いやすくなります。
また,例えば,贈与がなされた時期において,被相続人の認知症が重く,贈与について理解ができるような状態ではなかった場合も,贈与が不自然・不合理であると判断される可能性が高いと言えます。
【引き出した預金は被相続人の生活費として使用したものであるという反論】
更に,「引き出した預金は,被相続人本人の生活費のために支出した。」という反論がありえます。
このような反論がなされた場合も,引き出された金額や頻度,被相続人の状態や,生活状態,使い込みが疑われる者が預金を管理するようになった時期における引出金と従前の引出金とから,生活費として過剰な支出であることを主張することが考えられます。
例えば,従前,被相続人の生活費が20万円程度であったにもかかわらず,特段の事由が存在しないのに,使い込みが疑われる者が管理をしてから毎月100万円に近い金額が引き出されている等の事情がある場合,生活費として支出した旨の主張は不自然・不合理であると言いやすくなります。
被相続人死亡後の無断引き出しに対する反論
被相続人死亡後の引出に対しては,「葬儀費用として支出した」旨の反論がよくなされます。
もっとも,葬儀費用は喪主が負担すべきであると考えることが比較的多いといえるため(名古屋高裁平成24年3月29日判決),引き出した者が喪主であった場合,自ら負担すべき金銭を遺産から充てたことになります。
したがって,遺産である預金を引き出した者からこのような反論がなされた場合は,他の相続人が葬儀費用として使用することを承諾していたという事情が無い限り,預金を引き出した者の反論は認められない可能性が高いと言えます。
被相続人死亡前後に共通する反論
その他,被相続人死亡前後に共通する反論としては,
①「消滅時効が成立している」
②「遺産分割協議書を作成しているためもはや預金の引き出しの問題は解決済みである」
というものがあげられます。
まず,①の「消滅時効が成立している」という反論ですが,預金の無断引き出し・使い込みに対する返還請求の時効は,不当利得返還請求権に基づく請求の場合は,遺産である預金から引き出されてから10年(改正後の民法では,遺産である預金が引き出されたことを知った時から5年または権利を行使できるときから10年)になります。
他方で,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づいて請求を行う場合は,遺産である預金が引き出されたことを知った時から3年または引出から20年(改正後の民法も基本的には同様になります。)になります。
不当利得返還請求権に消滅時効が成立していたとしても,不法行為に基づく損害賠償請求権に消滅時効が成立していなければ返還請求をすることができますので,時効について心配する必要はあまりないことが多いです。
もっとも,10年以上前の引出の場合は,時効にかからないとしても当時の資料が残っていないことがよくあります。したがって,別途立証の問題が残るということに留意する必要があるでしょう。
次に,②の「遺産分割協議書を作成しているためもはや預金の無断引き出しの問題は解決済みである」という反論ですが,遺産分割協議書において,いわゆる「清算条項」と呼ばれる条項が存在しない場合は,遺産分割は今ある遺産を分ける手続であって,預金の無断引き出し(使い込み)の問題とは別であるため,あ熊で遺産分割協議書と預金の無断引き出しは別問題と言えます。
したがって,当該反論が認められない場合が多いと言えそうです。
遺産である預金の無断引き出し(使い込み)がなされた場合の具体的な解決手続
これまで遺産である預金の無断引き出し(使い込み)がなされた場合にどのような資料を集めるべきか,また,どのような反論がなされるかを解説致しました。
それでは,資料収集の結果,遺産である預金の無断引き出し(使い込み)が強く疑われる場合,どのような手続を経て解決まで進むことになるのでしょうか。
まず,預金を引き出した相手方が相続人であり,預金の無断引き出し(使い込み)を認めた場合は,遺産分割協議の中でまとめて解決をすることも可能です。
もっとも,預金を引き出した相手方が無断引き出しをしたことを認めるということは多くありません。多くの場合は,預金を引き出した者は,上で述べたような反論を行い返還をすることを拒みます。
その場合の解決方法ですが,民事訴訟を提起して不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権に基づいて返還請求を行うことがオーソドックスな手続と言えるでしょう。
民事訴訟を提起した場合,裁判期日が複数回開かれることになります。その後,双方で主張・立証の応酬を行い,その中で折り合いがつけば,和解による解決になることもあります。折り合いがつかない場合は判決ということになります。
終わりに
以上,遺産である預金の無断引き出し(使い込み)がなされた場合の対処法について解説を致しました。
遺産である預金の無断引き出し(使い込み)がなされた場合は,資料の収集・確認,相手方の反論の検討・対策等,手続の選択等,専門的知識が必要になります。
このような問題を解決するためには,預金の無断引き出し(使い込み)の問題を多く扱っている弁護士に依頼をすることがベストであると言えます。
東京都中野区に所在する吉口総合法律事務所では,預金の無断引き出し(使い込み)の問題を多数扱った経験があり,多数のノウハウや解決事例を有しています。
預金の無断引き出し(使い込み)に関し,ご相談がございましたら,中野区で相続無料法律相談対応の吉口総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。