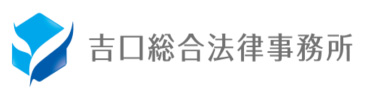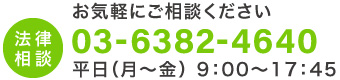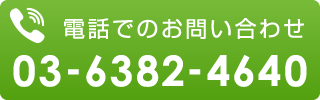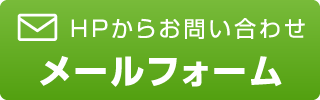Author Archive
【お知らせ】年末年始の営業について
弊所では、2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日)までの期間を年末年始休業とさせていただきます。
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】北区立赤羽文化センターで相続に関する区民講座を行いました
弊所の吉口弁護士が北区立赤羽文化センターの区民講座として、「相談事案から学ぶ!後悔しないための相続対策」と題する相続セミナーを行いました。
区民講座は8月31日(土)午前10時30分から正午までの間に行われましたが、区民講座において、区民の皆様から相続に関する多数のご質問をいただきました。
東京都中野区の吉口総合法律事務所では、今後も皆様のお役に立つよう情報発信を続けていきたいと考えております。
相続等の法律問題でお困りの方は弊所までお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】2024年夏季休業のお知らせ
弊所では、2024年8月13日(火)から8月16日(金)までの期間を夏季休業とさせていただきます。
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】「週刊エコノミスト」に共有物分割請求等に関する記事を執筆致しました
週刊エコノミスト(毎日新聞出版社)令和6年7月16日・23日号の特集記事『これから大変!マンション管理&空き家』にて、弁護士吉口が記事を執筆いたしました。
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240723/se1/00m/020/047000c
今回執筆した記事は「必読!空き家を“持たない&処分する”ための法的対策」というものであり、具体的には、法改正により設けられた新たな共有物分割請求の制度等を紹介したものになります。
相続や不動産問題にお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】「ちょこっと弁護士Q&A」に預貯金の使い込みに関する記事を執筆致しました
ポータルサイト「ちょこっと弁護士Q&A」にて相続預貯金の使い込みに対する対応方法に関する記事を執筆いたしました。
記事はこちらになります。
https://chokoben.com/media/sozokuyokin_henkan
預貯金の使い込みを含む相続問題にお困りの方は中野区東中野の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
年末年始の営業のお知らせ
弊所では、2023年12月27日(水)から1月8日(月)までの期間を年末年始休業とさせていただきます。
営業開始は1月9日(火)からとなります。何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】「週刊エコノミスト」に遺言書に関する記事を執筆致しました
週刊エコノミスト(毎日新聞出版社)令和5年11月14日号の特集記事『相続税必見対策』にて、弁護士吉口が記事を執筆いたしました。
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20231114/se1/00m/020/027000c
前回は空き家に関する記事を執筆を致しましたが、今回は「遺言書を書こう “争族”を避けるために」という記事になります。
相続や不動産問題にお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】「週刊エコノミスト」に空き家対策の記事を執筆いたしました
週刊エコノミスト(毎日新聞出版社)令和5年8月29日号の特集記事『どうする?!空き家&老朽マンション』にて、弁護士吉口が記事を執筆いたしました。
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230829/se1/00m/020/041000c
今回執筆をした記事は、「これでバッチリ! 空き家を持たないための六つの対策」というものです。
今後も皆様にわかりやすく法律情報をお伝えしたいと考えております。
相続や不動産問題にお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】2023年夏季休業のお知らせ
弊所では、2023年8月10日(木)から8月16日(水)までの期間を夏季休業とさせていただきます。
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。
【お知らせ】「週刊エコノミスト」に相続記事を執筆いたしました
週刊エコノミスト令和5年3月7日号の特集記事『4月施行目前! 相続&登記 法改正』にて、弁護士吉口が記事を執筆いたしました。
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230307/se1/00m/020/020000c
今後も皆様にわかりやすく法律情報をお伝えしたいと考えております。
相続や不動産問題にお困りの方は東京都中野区所在の吉口総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。