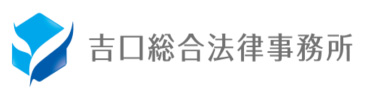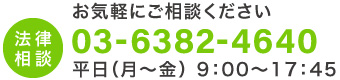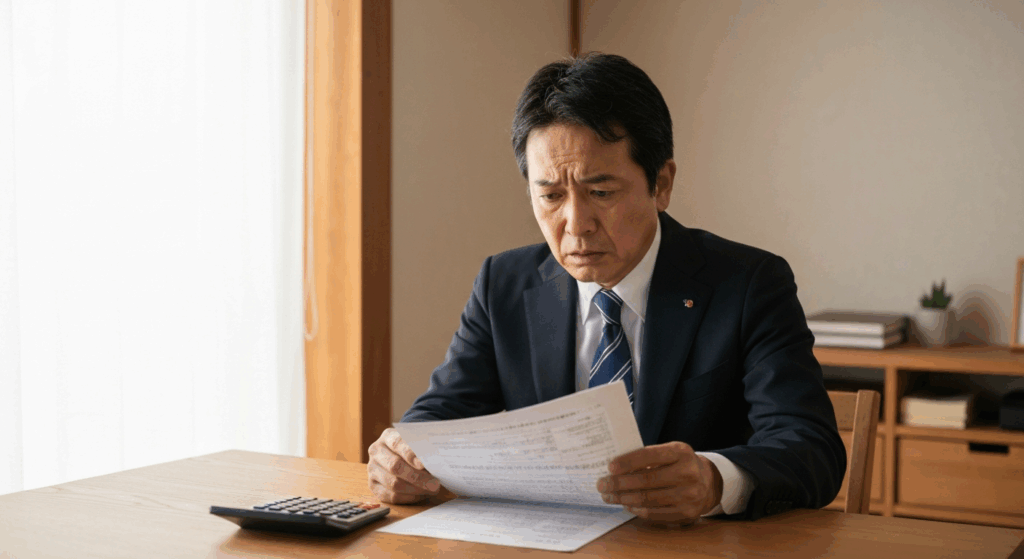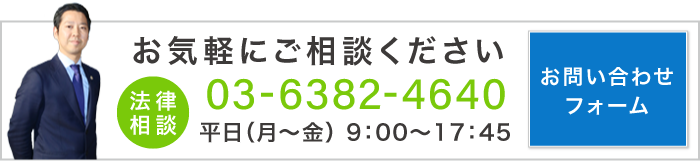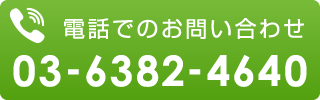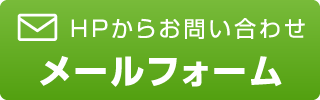目次
【解決事例】相手が動かない遺留分請求…こちらから訴訟を起こし長期紛争を解決
※以下の事例はご相談内容を元に当事者の属性等を修正したものになります。
遺留分侵害額請求を受けたものの、相手方からの連絡が途絶え、話が全く進まない――。このような状況は、請求された側にとって大きな精神的負担となります。「いつまでこの状態が続くのか」「このまま放置して大丈夫なのだろうか」という不安ばかりが募り、日常生活にも影響を及ぼしかねません。
当事務所では、まさにこのような膠着状態に陥ったご相談者様と共に、請求された側から主体的に訴訟を提起することで、長期化していた紛争を解決に導いた経験がございます。
本記事では、この事例をご紹介するとともに、遺留分請求を放置するリスクや、請求された側から取り得る対抗策について、弁護士が詳しく解説します。
ご相談の背景:遺留分請求はされたが、話が進まず時間だけが過ぎていく
ご相談者様(長女)は、お父様を亡くされ、相続を迎えました。お父様は生前、「全財産を長女に相続させる」という内容の遺言書を作成されていました。これに対し、他の妹4名から、内容証明郵便で遺留分侵害額請求が届きました。
ご相談者様としては、法律で定められた権利である以上、遺留分を支払う意思はありました。しかし、請求をしてきたご兄弟側から、具体的な遺留分額の提示や協議の申し入れが一切なく、時間だけが過ぎていきました。
遺産には複数の収益不動産や不動産管理会社の株式などが含まれており、財産評価も複雑です。関係者が多いことも相まってか、相手方もどう進めてよいか分からなくなっているのかもしれません。しかし、このままではいつまでも問題が解決せず、不動産の経営や今後の生活設計にも支障が出てしまいます。
このような膠着状態を打開したいとの思いで、当事務所にご相談に来られました。
解決への道筋:請求された側から「支払うべき金額」を確定させる訴訟を提起
通常、遺留分に関する訴訟は、請求する側が金銭の支払いを求めて提起するものです。しかし、本件のように請求する側が動かず紛争が長期化している場合には、請求された側から「支払うべき債務の不存在」あるいは「存在するとしても、その金額は〇〇円に限られる」ことを確認する訴訟(債務不存在確認訴訟など)を提起することが可能です。
当事務所では、ご相談者様が主体的に紛争を解決したいという強いご意向を踏まえ、この方法を選択しました。ご相談者様を原告として訴訟を提起し、こちらが相当と考える遺留分額を算定して裁判所に主張しました。これにより、相手方(被告)は裁判の場で具体的な反論をせざるを得なくなり、紛争の解決に向けて手続を進めることができました。
裁判では、やはり収益不動産や非上場である資産管理会社の株式、会社への役員貸付金などの評価額が主な争点となりました。また、法的な論点とは別に、算出された遺留分額をどのように支払うか(支払原資)も重要な課題でした。
最終的に、専門的な知見に基づき当方の主張を展開した結果、相手方の当初の請求見込み額を大幅に減額した内容で、裁判上の和解を成立させることができました。
また、遺留分の支払原資についても、不動産を原資とした資金調達が可能になり、これにより、長期間にわたる紛争に終止符を打ち、ご相談者様は安堵の表情を取り戻されました。
弁護士コメント:放置は危険!主体的な解決が重要です
遺留分を請求された側から、支払うべき金額を確定させるための法的手続きがあることは、あまり知られていません。今回の事例のように、この手続きを知らないために、ただ相手の出方を待つしかなく、貴重な時間が失われてしまうケースは少なくありません。
相手からの連絡が途絶えた場合、「このまま時効になるのでは?」と期待される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一度でも遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便など)がなされている場合、そこから5年間は金銭債権として時効にかかりません。つまり、5年が経過するまでの間は、いつ訴訟を起こされてもおかしくない不安定な状態が続くのです。
紛争を根本的に解決するためには、受け身の姿勢ではなく、今回の事例のように自ら訴訟を提起することも含め、主体的に解決を図ることが極めて重要です。
遺留分請求を放置するとどうなる?消滅時効の仕組みとリスク
「相手が請求してきたのに、その後何も言ってこない」という状況で、放置し続けることには大きなリスクが伴います。その理由を理解するために、遺留分の消滅時効の仕組みを知っておくことが重要です。
注意!遺留分の時効は「2段階」で進行する
遺留分侵害額請求権の時効は、実は2段階の構造になっています。
- 意思表示までの時効(1年または10年)
遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、請求の意思表示をしないと時効によって権利が消滅します。また、これらの事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年が経過したときも同様です。(民法1048条) - 金銭債権の時効(5年)
上記の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示(通常は内容証明郵便などで行われます)がなされると、遺留分は具体的な「金銭支払請求権」に変わります。この金銭債権は、一般的な債権と同様に、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効によって消滅します。(民法166条1項1号)
「請求後に放置」された場合の危険性
ご相談者のケースも含め、すでに相手方から内容証明郵便などで請求を受けている場合は、上記の「1年の時効」はクリアされており、相手方は遺産を取得した相続人に対して「5年間」有効な金銭債権を持っている状態だということです。
この状態で放置し続けると、以下のようなリスクが考えられます。
- 突然の訴訟提起:相手方の都合の良いタイミングで、ある日突然、裁判所から訴状が届く可能性があります。
- 遅延損害金の発生:具体的な請求額を伴って遺留分侵害額請求の意思表示が到達した場合、到達した日の翌日から、支払いが完了する日まで、法定利率(現在は年3%)による遅延損害金が発生し続けます。放置期間が長引くほど、支払うべき金額は膨らんでいきます。
- 精神的負担の継続:いつ請求が再開されるか分からないという不安定な状態が続き、精神的な平穏が害されます。
このように、「請求後の放置」は決して得策ではありません。むしろ、時間が経つほどご自身の立場が不利になる可能性もあります。
請求された側からの反論!遺留分額の主な争点とは
相手方から請求された金額を、そのまま受け入れる必要はありません。特に遺産の評価額については、大きな争点となることが多く、請求された側から適正な評価額を主張することで、支払額を減額できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をされた側の反論については、遺留分侵害額請求をされた場合どのように対応をすればよいかのページでも解説している通り、複数の反論があり得ます。

争点①:不動産の評価額はいつの時点で、どう決めるか
遺産に不動産が含まれる場合、遺産全体の評価額に対する割合が大きいことから、その評価額が遺留分の算定額に最も大きな影響を与えることが多いです。不動産の評価には、以下の点を理解しておくことが重要です。
- 評価の基準時:遺留分を算定する際の不動産の評価は、「相続開始時(被相続人が亡くなった時点)」の価額が基準となります。
- 評価の方法:不動産の評価額には、固定資産税評価額、路線価、公示価格など様々な指標がありますが、遺留分の算定においては、これらはあくまで参考に過ぎません。原則として、「実勢価格(時価)」、つまり実際に市場で売買されるであろう客観的な価額で評価されます。
多くの場合、請求する側は自分たちに有利な高い評価額を主張してきます。しかし、請求された側としては、不動産業者による査定や不動産鑑定士などの専門家に依頼して客観的な鑑定評価を取得し、適正な時価を主張することが重要です。どの評価方法を用いるかで、遺留分額は数百万円、数千万円単位で変わることも珍しくありません。
争点②:非上場株式の評価額はどう算定するか
冒頭の事例にもあったように、被相続人が同族会社を経営していた場合など、遺産に非上場株式が含まれることがあります。非上場株式は、上場株式のように客観的な市場価格がないため、その評価は非常に複雑で専門的です。
会社の純資産、収益性、配当実績、類似業種の他社の株価などを総合的に考慮して評価額を算定しますが、どの評価方法を重視するかによって、株価は大きく変動します。そのため、相手方が提示してきた評価額の根拠を精査し、必要であれば公認会計士や税理士といった専門家と連携して、こちらからも適切な評価額を算定・主張していくことが不可欠です。安易に相手の主張を鵜呑みにする必要はありません。
その他に確認すべきポイント(特別受益など)
財産評価以外にも、遺留分額を減額できる可能性のある要素として「特別受益」があります。
特別受益とは、遺留分を請求してきた相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益(贈与)のことです。例えば、以下のようなものが該当する可能性があります。
- マイホーム購入資金の援助
- 事業の開業資金の援助
- 多額の金銭の贈与
もし、請求者側にこのような特別受益があれば、それは遺産の前渡しとみなされ、遺留分額から控除できる可能性があります。過去の経緯を丁寧に振り返り、反論の材料がないか検討することが重要です。

長期化する遺留分トラブルは弁護士にご相談ください
遺留分侵害額請求をされたものの、相手が動いてくれずにお困りの方へ。これまで解説してきたように、この問題を放置し続けることには多くのリスクが伴います。不動産や非上場株式の評価、特別受益の主張など、遺留分を巡る争いは法的に極めて専門的であり、ご自身だけで対応するには限界があります。
相手の動きが止まっている今こそ、こちらから主体的に動き、問題を解決に導く必要がございます。当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、膠着した状況を打開するための最善の策をご提案いたします。
当事務所は相続・不動産分野に注力しており、財産評価が絡む事案にも対応しています。ご相談から事件終了まで、一人の弁護士が一貫して担当し、進捗を丁寧にご報告することで、ご依頼者様の不安を少しでも和らげられるよう努めています。
「このままでは埒が明かない」「専門家の意見を聞きたい」とお考えでしたら、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたが一歩前に進むためのお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。