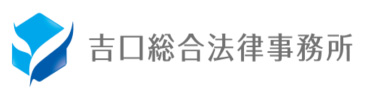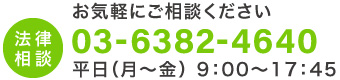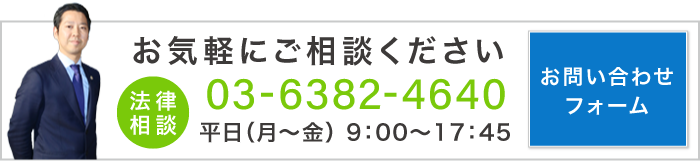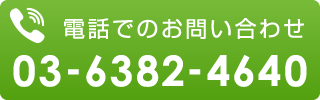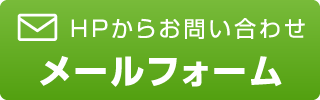遺言書の作成増加に伴い、遺留分侵害額請求のご相談が増加しています。
特に、「請求が遅れたため、消滅時効が成立している」と相手方から主張され、ご不安になるケースは少なくありません。
遺留分侵害額請求の消滅時効は、相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年という短期間です。この短い時効を主張された場合、どのように対応すべきでしょうか。
本コラムでは、遺言書が届いたにもかかわらず「知らなかった」という具体的な事情をもって相手方の時効の主張を排斥した解決事例を、弁護士が詳しく解説します。
※ 本コラムの事案は、特定の状況を分かりやすく説明するため、事実にデフォルメを施しています。個別の事案により結論は異なりますので、具体的なご相談は弁護士までお願いいたします。
● 関連する内部リンク(当事務所のウェブサイトより)
- 遺留分侵害額請求全般について詳しく知りたい方はこちら:遺留分侵害額請求とは?弁護士に依頼するメリット
-
遺留分侵害額請求に対する反論について詳しく知りたい方はこちら:遺留分侵害額請求をされた際の有効な反論と対策
目次
事例の概要と問題の所在
問題となった事例の概略は次のようなものでした。
| 項目 | 内容 |
| 相続関係 | 被相続人(父)の相続人は子二人の姉妹 |
| 遺言の内容 | 「全財産を姉に取得させる」という内容の遺言書を作成 |
| 経緯 |
・遺言書では遺言執行者が指定されており、遺言執行者が妹の自宅に遺言書と財産目録を郵送した。 ・その後、妹が遺留分侵害額請求の内容証明郵便を姉に発送(妹が父の死亡を知ったのが父の死亡から約2年後であったため、死亡を知ってから直ちに発送。) |
| 問題の所在 | 相手方(姉)が、遺留分侵害額請求の消滅時効(1年)が成立しているとして支払いを拒否 |
遺留分侵害額請求の根拠となる民法第1048条は以下の通り、請求期間を厳しく定めています。
民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第百四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(出典:e-Gov法令検索 民法)
本件の最大の争点は、遺留分権利者である依頼者様が、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」がいつか、という点でした。
相手方の主張
相手方である姉は、この条文と遺言執行者から妹の自宅に遺言書の写しが郵送されている事実を根拠に、以下の主張を展開しました。
-
時効期間の徒過:請求が死亡から2年後であり、遺言書送付から1年を経過しているため、消滅時効は成立している。
-
了知の可能性:遺言書が自宅に郵送された時点で、依頼者は遺言の内容(遺留分侵害の事実)を「了知する可能性」があった。民法第1048条の「知った時」は、現実的な認識は不要で、了知可能性があれば足りる。
解決のための手段
当事務所は、相手方の消滅時効の主張を排斥するため、依頼者である妹様が、遺言書が送付されたときに遺言書の内容を「知った」わけではないという具体的事情を主張・立証する戦略をとりました。
1. 弁護士による具体的な反論
民法1048条の「知った時」は、単に書類が届いたという形式的な事実ではなく、遺留分権利者本人が現実的・具体的に事実を認識した時点でなければならないと主張しました。
そして、本件では具体的に事実を認識したどころか、一般的抽象的にも事実を認識していないと反論しました。
2. 証拠の収集・提出
反論を裏付けるため、以下の客観的な証拠を収集し、裁判所に提出しました。
-
施設の入所記録:遺言執行者からの遺言書送付当時、依頼者様が自宅におらず、継続的に施設に入所していた事実を立証。
-
面会状況の記録:ご家族が、依頼者の体調不良や面会制限を考慮し、父の死亡の事実や遺言書が送付された事実を依頼者様に伝えていなかった事実を立証。
3. 裁判所の判断と結果
これらの立証活動の結果、裁判所は、依頼者様が「相続の開始と遺留分侵害の事実を現実的・具体的に認識したとは認められない」と判断し、相手方の消滅時効の主張を排斥しました。また、相手方の抽象的な「了知する可能性があれば足りる」という主張も退けられました。
最終的に、依頼者様の遺留分侵害額請求が認められ、無事に金銭を取得することができました。
遺留分トラブルや消滅時効の紛争を未然に防ぐためには
本件の紛争は、遺言書が特定の相続人に全てを相続させる内容であったことと、遺留分侵害額請求の時効期間の短さから生じました。
-
遺言作成時の遺留分への配慮:遺言書を作成する立場である場合には、遺言書を作成する際に遺留分を侵害しない内容とするなど、紛争予防の措置を講じることが重要です。
-
相続発生後の迅速な行動:相続が発生した場合、遺言の有無や内容を確認したら、時効期間のカウントダウンが始まります。権利を失わないよう、速やかに弁護士に相談し、請求の意思決定と準備を迅速に行うことが不可欠です。
-
家族間の重要な情報共有:ご本人への配慮から情報の伝達を控えるケースもありますが、法的な権利に関わる重要な情報(死亡、遺言書など)については、体調を考慮しつつも、情報を伝える時期や方法を専門家と相談することが重要です。
弁護士からのコメント
遺留分侵害額請求における消滅時効は、依頼者様の権利が消滅するか否かの死活問題となるため、裁判でも徹底的に争われる論点です。
本事例が示す通り、単に書類が届いたという形式的な事実だけでは時効は完成しません。
一方で通常は、遺言書等の遺留分を侵害していることを裏付ける書類が届いたのであればその時点で相続の開始と遺言により遺留分が侵害されていることを知ったのではないかと考えられてしまうこともあります。したがって、遺留分を請求する側でもそうではないことを具体的に主張・立証する必要があります。
依頼者様ご本人の「知ることができなかった」という具体的な事情と客観的な証拠を積み重ねることによって、ようやく時効の主張を排斥することが可能となります。
「遺言書の存在を知るのが遅れた」「もう時効かもしれない」と不安を感じている方も、諦める前に一度、相続に強い弁護士にご相談ください。個別の事情を法的 に検討し、権利実現に向けて迅速に対応いたします。
東京都中野区所在の吉口総合法律事務所では、遺留分侵害額請求を行う側・請求された側のいずれの立場のご相談も承っております。遺留分トラブルや消滅時効の主張でお困りの方は、東京都中野区を拠点とする弊所までお気軽にご相談ください。

代表弁護士の吉口 直希です。
東京都中野区の「吉口総合法律事務所」は、JR総武線「東中野」駅西口より徒歩30秒のアクセスしやすい法律事務所です。
相続・遺言、離婚・男女問題、借金問題、など、身の回りの法律問題全般に対応しております。地域に根ざしつつ、全国からのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
弊所では、相続、離婚等の一部業務について30分無料面談相談を行っております。また、事前のご予約いただければ夜間のご相談にも対応可能です。お一人で悩まず、まずはあなたの状況をお聞かせください。